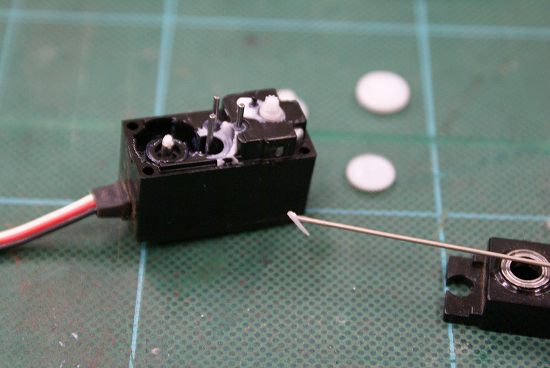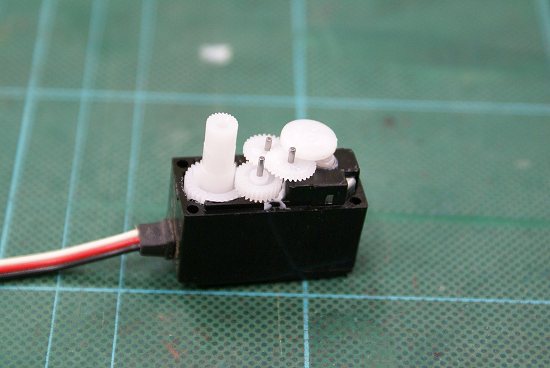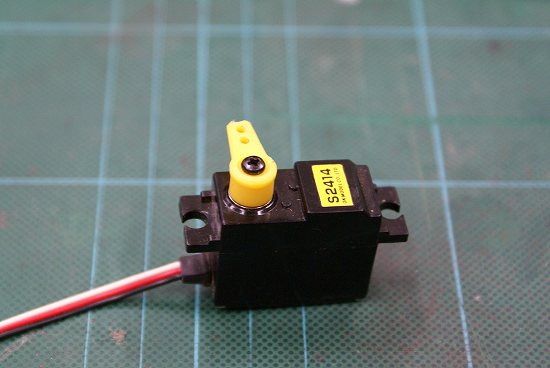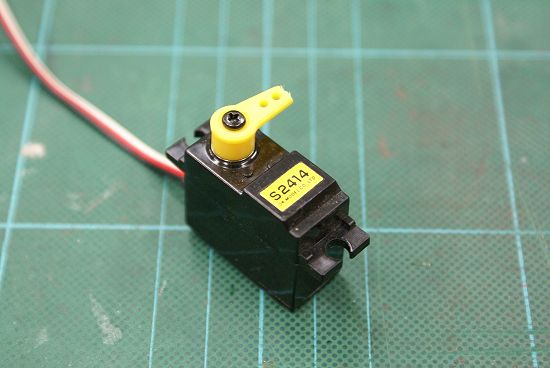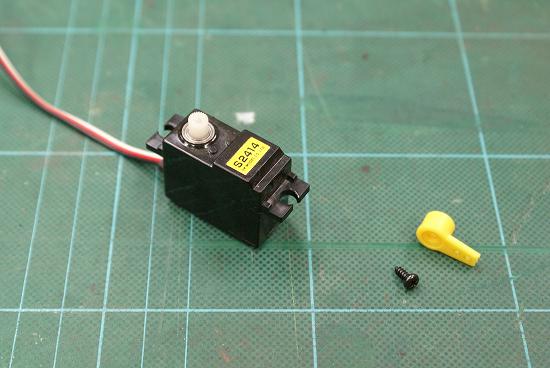先日、OK模型さんの新作DF機の「アルバトロス」を飛ばすとのことで、ちょっとお邪魔しました。
当日は、RCAWさん・ラジ技さんも取材に来ていましたのでOK製の他のDF機も飛ばすとのことです。 先ずは、ミラージュです。
先ずは、ミラージュです。
相変わらずのスピードに乗ったパワフルな飛びを見せています。
スピードが速いのと機体が小さいのとで各誌のカメラマンもベストショットを撮影するのに一苦労していました。
 続いて、ミグ15の飛行です。
続いて、ミグ15の飛行です。
こちらは、機体が一回り大きいので撮影用に若干スピードを落としても安定して飛んでくれるので、撮影も楽です。
ミグは、69mmのパワフルDFと機体の吸気形状ともあいまってフルパワーで飛行していると、ジェットエンジンのような吸気音が聞こえより実機らしい飛びをしています。
 今日のお目当ては、このアルバトロスです。
今日のお目当ては、このアルバトロスです。
使用しているDFはミグと同じ69mmの物が使用されています。
機体サイズも後方に移ってるミグと比較すると分かりますがほぼ同じぐらいの大きさで機首の形状で少し全長が長く感じます。
 発進は、他の機体と同じようにキットに付属のショックコードを使用します。
発進は、他の機体と同じようにキットに付属のショックコードを使用します。
フルパワーにして手を離すのですが、手を離す前に少しアップを引いておいて手を離して一瞬して引いていたアップを戻してやるのが綺麗な発進のコツとのことでした。
機体は、すぐに機速を上げて上昇して行きます。
 機速がついてしまうとジェット機らしいスピードに乗った飛びを見ててくれます。
機速がついてしまうとジェット機らしいスピードに乗った飛びを見ててくれます。
機体の吸気口の形状のせいか、ミグより吸気音は、静かなようです。
機体形状も違うのでミグとは、一味違う雰囲気です。
ジェットエンジンは、やってみたいけどまだまだ高値の華で、飛ばす場所も安全性の問題もあり、限られたところでしか飛ばせないなどいろんな制約があって出来ないと思っている方などは、このDF機でよりジェット機に近いフィーリングを体験してみてはいかがですか。