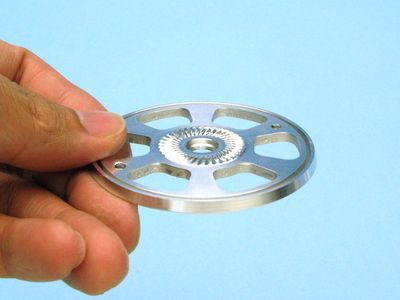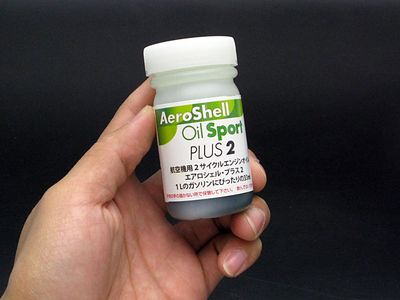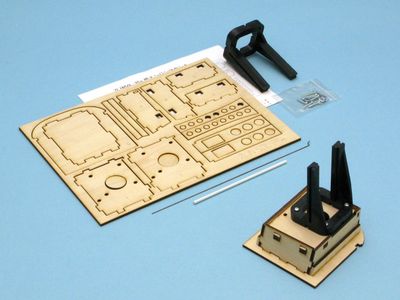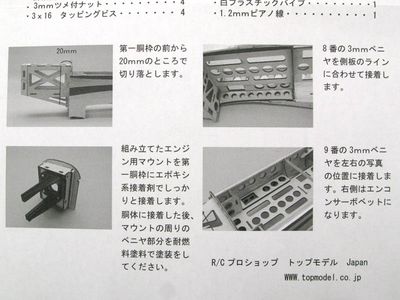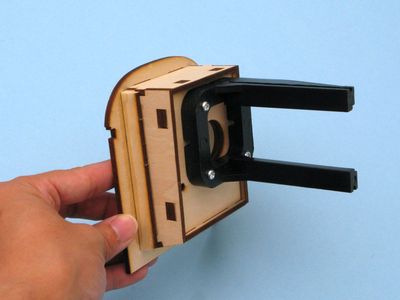ロングセラーのABスピンナーには、57mmサイズにのみ、
「タイプR」という商品が存在します。

こちらがその、PILOT ABスピンナー タイプR 57mm 白。

同じサイズのABスピンナーPILOT ABスピンナー 57mm 白と比べても、
外観だけではバックプレートの色の違いでしか見分けがつきません。
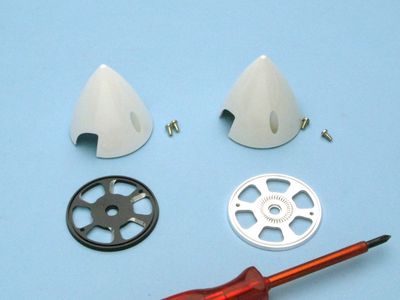
そのバックプレートが、色以外にどう違うのか、見てみることにします。

そして、タイプR。肉抜き部分が斜めに削られているのがお分かり頂けますか?
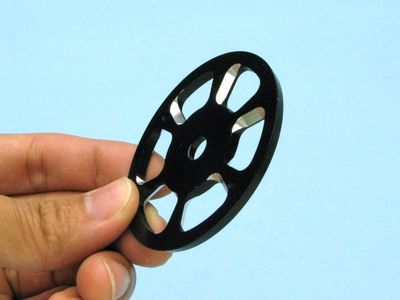
もちろん、裏面も削られています。
このバックプレートがスピンナーと一緒に回転し、ファンのような働きをして
エンジンやモーターに風を強制的に送り込むによって、
冷却効果が上がるというわけですね。
ただ、中央部分の滑り止め加工がタイプRにはありませんので、
滑り止めにPILOT グリップワッシャー Sなどを使用する必要があります。
では次回は、ABスピンナーそのものの特長をご紹介しようと思います。