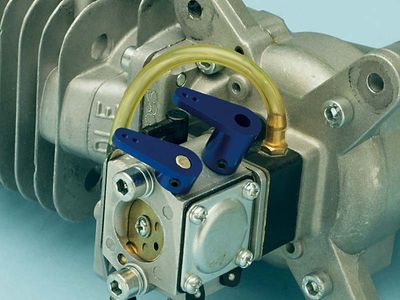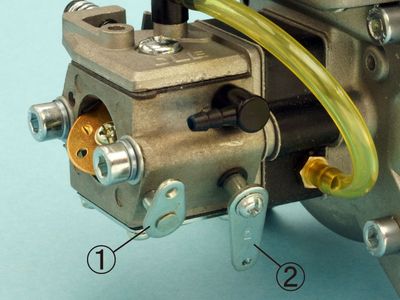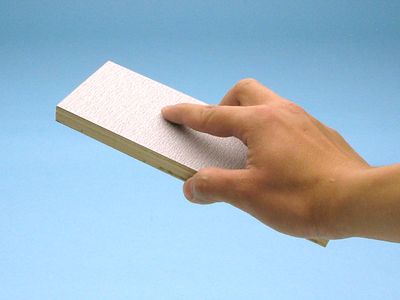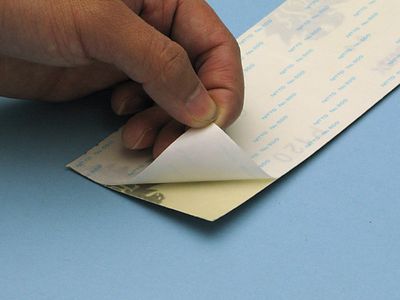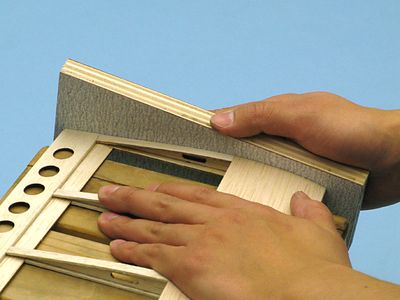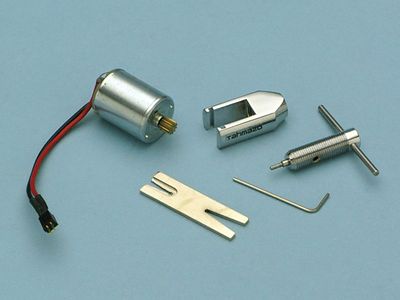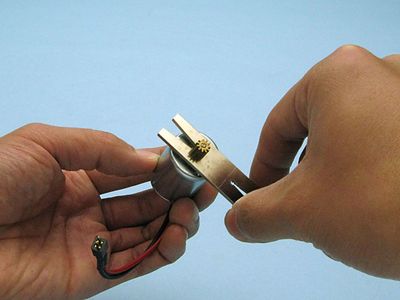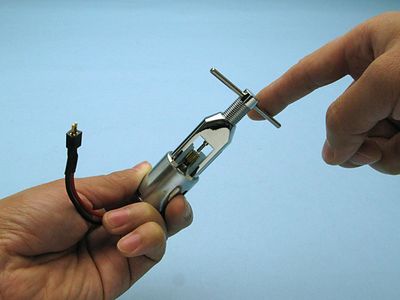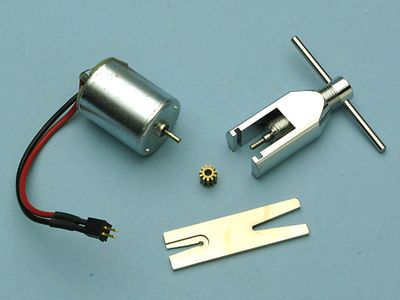今回ご紹介するのは、
新発売のTOPMODEL ハイパワーリダクションスターター。
当店オリジナルのスターター第2弾です。
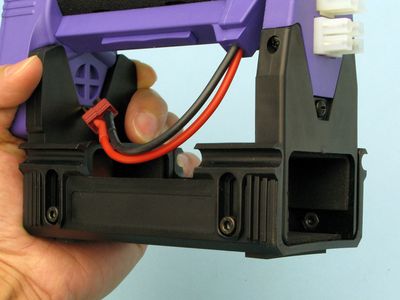
このバッテリーケース。
バッテリーケースにバッテリーを積むことができるので、コードレスのスターターとして使うことができるんです。
さらにこのスペースは、六角レンチ(3mm)でネジを緩めるだけで、
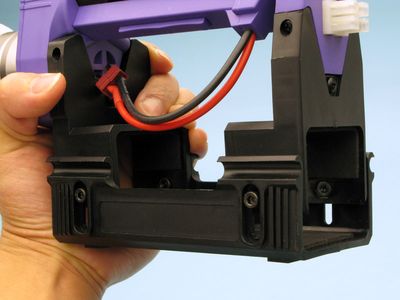
高さが31mm~46mmまで、簡単に調節可能になっています。(幅は約48mm)
使用したいパワーに応じて、色々なバッテリーが使用可能になっているんです。
18Vまで対応しているので、4セルリポバッテリーも使えます。
当店オリジナルのTLB 14.8V4400mAhも、バッテリーケースにちゃんと入りますよ。
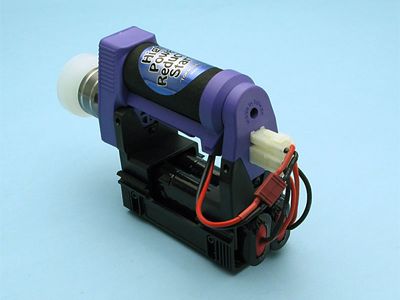
RCカー用の7.2VNixxバッテリーパックを2本直列で繋いでみました。
ピッタリ入ります。

このスペースは前後方向に仕切りがされていませんので、
バッテリーが多少長くても問題なく積むことができます。

また、ワニ口クリップ(コード、コネクター付き)が入っていますので、バッテリーがあがってしまい使えない場合でも、12Vの鉛バッテリーが使えて安心です。
サッと使える、便利なスターターですよ。