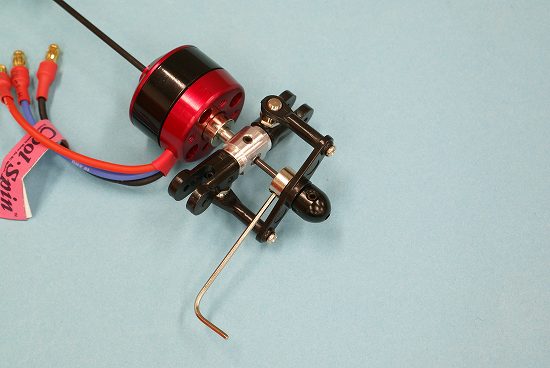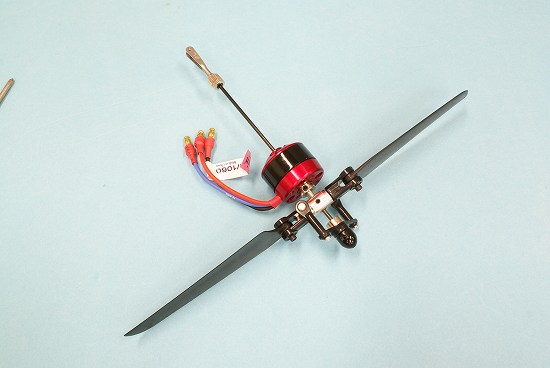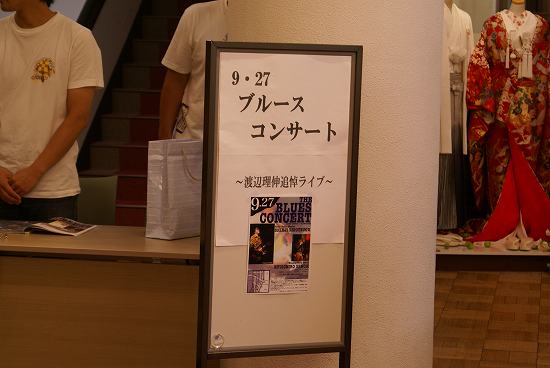モーターグライダーとしての地上からのフライトテストをした数日後、いつものスロープにいい風が入っているとのことで、スロープでのテストに行こうということになりました。
 当日は、午後から5m~8mの風が吹く絶好のコンデションで、現地に到着後、機体の準備とチェックをすませて、早速フライトにはいります。
当日は、午後から5m~8mの風が吹く絶好のコンデションで、現地に到着後、機体の準備とチェックをすませて、早速フライトにはいります。
さすがにモーターランをすることも無く、谷に向いて手を離れた機体は、スロープから駆け上がってくる最高の上昇風にのっていとも簡単に飛んでいます。
 機体は、風に乗ってどんどん上昇していきます。
機体は、風に乗ってどんどん上昇していきます。
前回のテストフライトで少しアップ癖があるので、主翼の仰角を主翼後方で3mmほど上げて調整したとのことで、癖も収まりスムーズに飛行しています。

長い翼をゆっくり大きくバンクして旋回するときの優雅さは、大型グライダーならでわです。
パワーユニットを搭載したモーターグライダーで、同系ピュアグライダーの「ELIXIR 3.2m」より重量が重いのですが飛んでいる感じを見ているとこのぐらいの重量がベストマッチしているようです。
 次に高度を取ってダイブで機速を上げて進入してきます。
次に高度を取ってダイブで機速を上げて進入してきます。
本格シャーレ機ほどでは、ないですが結構な速度で走っています。
 スピードに乗った機体が自分の目線より下の目前を通過する快感は、スロープソアリングを絶好のコンデションで体験した人をとりこにしてしまいます。
スピードに乗った機体が自分の目線より下の目前を通過する快感は、スロープソアリングを絶好のコンデションで体験した人をとりこにしてしまいます。
 この機体で以外に感じたのが、高速飛行をした時に風きり音の少なさです。
この機体で以外に感じたのが、高速飛行をした時に風きり音の少なさです。
これは、主翼の性能の良さを示しています。
 一通りの飛行を終えて着陸のために機体を一旦谷下に持って行き着陸点にむかって上昇進入して速度を落としてきます。
一通りの飛行を終えて着陸のために機体を一旦谷下に持って行き着陸点にむかって上昇進入して速度を落としてきます。
さすがに大型機で結構下からの進入となります。
 着陸地点近くでフラップ・エルロンでバタフライミキシングを作動してブレーキをかけて着陸となります。
着陸地点近くでフラップ・エルロンでバタフライミキシングを作動してブレーキをかけて着陸となります。
その後、私を含めメンバーが交代で操縦させてもらったのですが、機体が大きいので、スティックに対して舵の効きがマイルドで余裕を持って操縦をすることが出来ます。
グライダーは、翼長が2mを超えると翼の効率が良くなるものの、さすがに3mオーバーの機体の効率は、格段に良く一度その感覚を味わってしまうと病みつきになってしまいそうです。
皆さんも、是非大型グライダーにチャレンジしてみたは、いかがでしょうか。
 本機は、翼長2420mm・全長1960mmと非常にボリュームのある機体で大型スケールグライダーなどの曳航機として開発されたきたいです。
本機は、翼長2420mm・全長1960mmと非常にボリュームのある機体で大型スケールグライダーなどの曳航機として開発されたきたいです。 大型フラップを装備して、曳航機として有名な「ピラタス ターボ ポーター」同様に上空から急降下での短距離着陸を可能にしています。
大型フラップを装備して、曳航機として有名な「ピラタス ターボ ポーター」同様に上空から急降下での短距離着陸を可能にしています。 キットは、大型機のARFのため、機体全長のほぼ2m近い長さの大きな箱に入っています。
キットは、大型機のARFのため、機体全長のほぼ2m近い長さの大きな箱に入っています。 キットの中身を出してみました。
キットの中身を出してみました。